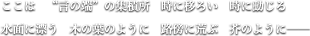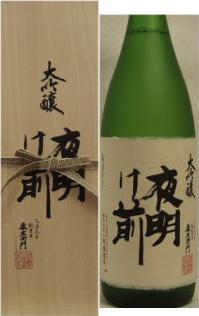綴るありきたりの言葉すら
陳腐に思えてしまう
愛戀 (あいれん)
哀戀 (あいれん)
溢愛 (いつあい)
逸愛 (いつあい)
溶愛 (ようあい)
蓉愛 (ようあい)
麗戀慕(れいれんぼ)
零戀慕(れいれんぼ)
。。。。。
幾ら言葉を造っても 足らない
思いが埋まらない。。
たゐに
たゐに【大為爾】
たゐにいで なつむわれをぞ
きみめすと あさりおひゆく
やましろの うちゑへるこら
もはほせよ えふねかけぬ
田居に出で 菜摘む我をぞ
君召すと 求食り追ひ行く
山城の 打ち酔へる子ら
藻は干せよ え舟繋けぬ
〔「大為爾」は四七字の初めの三文字の万葉仮名より〕
四七字の仮名を繰り返さずに、全部使って作られた五七調の歌詞。「あめつちの詞」に次ぐもので、平安中期頃の「いろは歌」に先行して作られたと考えられる。源為憲の「口遊(くちずさみ)」(970年成立)に見える。
あめつちのことば
あめつちのことば【天地の詞】
あめ つち ほし そら やま かは
みね たに くも きり むろ こけ
ひと いぬ うへ すゑ ゆわ さる
おふせよ えのえを なれゐて
天 土 星 空 山 川
峰 谷 雲 霧 室 苔
人 犬 上 末 硫黄 猿
生ふせよ 榎の枝を 馴れ居て
四八の仮名を重複させずに全部使って作られており、「え」が二度繰り返されるのは当時ア行のエとヤ行のエが音節として区別されていたことを示す。
「いろは歌」「たゐに」に先行して作られたと考えられる。あめつちの歌。
せっせんげ
- せっせんげ【雪山偈】
-
涅槃経(ねはんぎよう)に出る四句の偈(げ)「諸行無常・是生滅法・生滅滅已・寂滅為楽」のこと。
釈迦が雪山童子として修行していたとき、帝釈天が羅刹(らせつ)に変じて現れ、前半のみを説いた。釈迦は後半を聞くために身体を羅刹に与えたという。いろは歌はこの偈の意をとったものという。
諸行無常偈
- しょぎょうむじょう【諸行無常】
- 〔仏〕 仏教の基本的教義である三法印の一。この世の中のあらゆるものは変化・生滅してとどまらないこと。この世のすべてが儚いこと。
- ぜしょうめっぽう 【是生滅法】
-
〔仏〕〔「涅槃経」にある諸行無常偈の一句〕
あらゆる事物は変化し移ろいゆくということこそ生滅の法則だ、という意。 - しょうめつめつい【生滅滅已】
- 〔仏〕 生死を超えて涅槃(ねはん)に入ること。
- じゃくめついらく【寂滅為楽】
- 涅槃経の偈(げ)にある語。寂滅が真の楽しみである、の意。
自己愛
己が 己で在るために 何をすべきか
知っているのは 己だけ
切欠は 何処にでも 其処 彼処
それを拾うのは 己の感性
風の吹くまま 気の向くまま
己が魂の命ずるまま
自身のポテンシャルに気付いた人よ
真摯に 愚直に 直向きたれ──
己の波動を感じるからこそ
他の波動を感じられる
他の波動を感じるからこそ
己の波動を感じられる
自己愛とは
自身が 自身に向ける 究極の制御──
この制御を 純粋に行っておれば
他の 陳腐な幻惑に 揺らぐことはない
機会と覇気
- ふへん【不変】
-
(名・形動)[文]ナリ
変わらない・こと(さま)。
⇔可変
「─の真理」「永劫─」 - かへん【可変】
-
変えることができること。変わることができること。
⇔不変
「─式」
- ふへん-しんにょ【不変真如】
-
〔仏〕 真如の時間・空間を超越し、不生不滅であり、変わることのない相。真如の実相。
⇔随縁(ずいえん)真如 - ずいえん-しんにょ【随縁真如】
-
〔仏〕 本来不変である真如のあり方に対し、縁によって種々の現象として生じる真如のあり方。
⇔不変真如
こんなことをして ひとり遊びする。。笑
分からないことを分からない儘で済ますと
知る機会と知ろうとする覇気を失う──